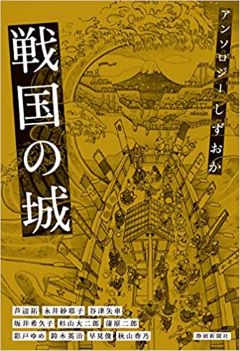「あ~あ」
ため息ばかりついているこの男、時代小説で食べている物書Hだ。ある秋の昼下がり、さくら市にやって来た。アイデアが授からないかと虫のいい了見を起こし、小説の主人公としている喜連川藩七代目藩主恵氏の墓所、龍光寺を詣でる。
本堂には源義家が久慈川の渕で見つけた玉が観音像と共に安置されている。護娠玉と呼ばれ、安産のお守りとされているそうだ。毎度のこと、執筆ははかどらず新作は難産だ。作品の安産を祈願し、境内にたたずむ。
「恵氏公、何卒、いいアイデアください」
調子よくHは願い、空を見上げた。青空に鱗雲が白く光っている。色なき風が頬を撫で、木々の枝を揺らした。
都合よくアイデアなど得られなかったが、書けるという根拠なき自信だけは抱き、龍光寺を後にする。
旧奥州街道に出たところで眼前を白い物が過ぎった。脳天にちくりと刺されたような痛みを感じ、同時に柔らく温かい透明のベールに包まれた……。
何だか幸せな気分になり、目についたカフェに入る。さくら市を訪れてウイスキーを飲まない手はないとハイボールを頼んだ。さくら市はウイスキーの町なのだ。
カウンターに座り、唐揚げを肴にハイボールを飲んでいるとカップルの会話が耳に入ってくる。弥五郎の森にあるウイスキー工場には十八万もの樽があり、原酒の再貯蔵が行われているのだとか。ボトルに詰める前、もう一度樽の中で数ヶ月から二年の時を過ごすそうだ。
「でね、再貯蔵をマリッジ(結婚)って言うんだって」
彼女は彼に左手でグラスを掲げて見せた。琥珀色の液体がたゆたうグラスを握る薬指に、婚約指輪が幸福の輝きを放っている。
Hは笑みをこぼし、ブレンドウイスキーのトワイスアップを頼んだ。店内に第三の男のメロデイ―が流れた。昔、見たCMが思い出される。オーソン・ウェルズが映画造りでいつも完璧を目指しているが未だに夢だ、しかし、このウイスキーは完璧だと賞賛していた。
完璧には程遠い自分の小説に自嘲気味の笑みを浮かべ、完璧なブレンドウイスキーを味わう。
一週間後、Hは新作を書き上げ、原稿を出版社にメールで送付した。旧奥州街道で感じた、ちくりと脳天を刺されたような痛みと透明のベール、あれは天使に矢を射掛けられたのではないか、お蔭で筆は進んだ。
あくる日、編集者から電話がかかってきた。
「面白かったですよ。筆が乗ってますね。恵氏の動きが軽快で……」
小説の天使が舞い降りたかとHは幸福な気分に浸った。
すると、
「それはいいんですけど……各話の最後、締め括りの箇所が抜けているんですよ。完成原稿を送って頂けませんか」
作品は七十から八十頁の話が四つで構成されている。
「最後の箇所……」
「尻切れトンボになっていて……話の流れからすると、二、三頁、足りないんです。完成前の原稿ファイルを送られたんじゃないですか」
確認して送り直しますと電話を切り、Hはパソコンをチェックした。送ったのが完成原稿だがなるほど各話、最後の箇所が抜けていた。確かに書いたはずだ。何かの拍子に削除してしまったのか……。
と、
「もしかして」
失われた頁は原稿量からして約三パーセントだ。樽熟成中のウイスキーは一年で二、三パーセント減少する。これを天使の分け前と呼んでいる。天使に助けられ、出来上がった作品、天使に分け前を捧げるのは当然だ。Hは感謝が足りなかったと反省しつつ原稿を完成させた。
ほっとしていると、
「ウイスキー、飲んでいるでしょう」
家人がウイスキーを持って来た。禁酒を誓ったHを家人は責めるような目で見る。
「飲んでないよ」
「嘘、減っているじゃない」
家人はウイスキーの瓶を突きつけた。
「ああ、それはエンジェルズシェアだ」